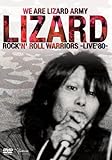先々週書いたNYLON100%のイベントだが、そのタイトル、ナイロン100パーセントとは、渋谷にあった小さなお店の名前だ。いわゆるロック喫茶というか、そのカウンターともいうべき店だったナイロン。壁は全て白塗り。テーブルや椅子もイタリアあたりの近未来風デザイン。通常のロック喫茶が暗く暑苦しい場所であったのに対して、どこまでも快適で明るい店だった。
 店内に流れる音はクラフトワークやノイ、デュッセルドルフ(全てドイツのグループ名称)あたりだった。後年、流れはニューウェーブへとシフトしていくが、とにかく、一日中クールな音を奏でていたのは確かである。
店内に流れる音はクラフトワークやノイ、デュッセルドルフ(全てドイツのグループ名称)あたりだった。後年、流れはニューウェーブへとシフトしていくが、とにかく、一日中クールな音を奏でていたのは確かである。
70年半ばからシンセサイザーの導入を考えていた私たちも、よく遊びにいった。特に、キーボードのコーと打ち合わせたり、待ち合わせたりするのに使っていたのがこの店だった。コーは店の開店当初からの常連客だったのだ。ドイツ人とのクォーターである彼は、この店でビールを舐めている姿がよく似合った。
 店内に流れる音はクラフトワークやノイ、デュッセルドルフ(全てドイツのグループ名称)あたりだった。後年、流れはニューウェーブへとシフトしていくが、とにかく、一日中クールな音を奏でていたのは確かである。
店内に流れる音はクラフトワークやノイ、デュッセルドルフ(全てドイツのグループ名称)あたりだった。後年、流れはニューウェーブへとシフトしていくが、とにかく、一日中クールな音を奏でていたのは確かである。70年半ばからシンセサイザーの導入を考えていた私たちも、よく遊びにいった。特に、キーボードのコーと打ち合わせたり、待ち合わせたりするのに使っていたのがこの店だった。コーは店の開店当初からの常連客だったのだ。ドイツ人とのクォーターである彼は、この店でビールを舐めている姿がよく似合った。
当然、このような店は他になかった。ごく初期はヨーロッパのインダストリアルなポップを求めて客がやってきた。そして、1980年、東京のアンダーグラウンドバンドが立て続けにデビューする中で、テクノポップなる用語が浮上した以後は、店はテクノポップの牙城とも目されていくのである。
ただし、店の名誉のため書いておこう。世に言うテクノポップブームと店は、音楽傾向において一線を画している、そのことは言っておかねばならない。この店でながれる音は、インダストリアルな、ハイテクが産み落とす『今の』音、現在ただいまの溜息だったのである。流行とかキャッチコピーとは無縁だった。
東京ロッカーズが既存のライブハウスではなく、リハーサルスタジオでの定期的ライブ演奏から活動を展開したことがきっかけとなり、それ以後、様々な場所やお店、小さなスペースでのライブ、パフォーマンスがあちこちで開催されるようになったのだが、この店では、それまでの趣味を継承し、シンセサイザーやリズムマシーンなど、ハイテクを駆使したコンパクトなバンドセットでのそれが企画されるようになった。そうした流れにおいては、かの時代、テクノポップの流れと混交して眺められるのは避けがたいことだった。
その店のコンセプトを打ち出していた、中村くんという人物がいる。彼が、今回、その店に来ていた連中によって生み出された音楽傾向や、その店を媒介にして起こった何かを鮮明にするため、一冊の本をプランニングした。つまり、多くの人間の目をもって眺めた景色、ナイロンを語ってもらい、音楽あるいは芸術制作者のサロンとしてのそれを明晰にしようとしたのである。私が行ったライブ、代官山での2日間のイベントは、その出版を記念するものだったのだ。
この店の初期には、よく顔を出していた。この店で飲むビールが大好きだったのである。ただ、残念なことにイベントが企画されるようになってからは足が遠のいた。すでに私自身が、ある程度に売れてしまったミュージシャンでもあった。ために行くのを控えるようになったのだ。ナイロンに来る客層が、リザードのファンとかぶっていたからである。
ロフトにしろ、ナイロンにしろ、ファンが待ち受けていたり、アーティスト志望の若者がデモテープを渡そうとしたりする。そのような場所に、自ら出かけていく馬鹿はそういない。そのうえに、である。ナイロンは数十人も入れば満員になる。小さなスペースだ。その貴重なスペースを消費するわけにはいかないではないか。
だから、いま思えば残念だが、私自身はこうしたサロンとしてのナイロンを経験していないのだ。それだけに、これから明晰にされるであろうそうした歴史、そうした空間認識を私は楽しみにしているのである。かつて何が起きていたかを知ることは、今後、何をなすべきかを考える上で重要な示唆を与えてくれる。ふたたび走り出す道筋を教えてくれるだろう。
敏感な方なら感じていることだろう。いま随所に分散・飛散していた力がひとつに結集しつつある。中途半端に売れるためや世過ぎのためでなく、まさに、自分たちの未来という、最重要なものがかかっている。ボランティアなんかじゃないんだ。30年前に同じく、売名のために分裂策動に走る愚か者が出るのは否めない。が、心の底まで開陳した仲間たちが集えば、ネガティブな意見は一顧だにしないで歩いていけるだろう。
眼前に広がるのは果てしない砂の海かもしれない。が、それでも、だ。そこを渡っていかなければ未来は開けない。
Momoyo The LIZARD 管原保雄
< http://www.babylonic.com/
>