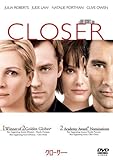 ●いつまでたっても解決しない男女の関係
●いつまでたっても解決しない男女の関係マイク・ニコルズが監督した「クローサー」(2004年)は、かつてジャック・ニコルソンとアート・ガーファンクルが出演した「愛の狩人」(1971年)のテーマを継続していて、三十年以上たつのにニコルズさんは未だに解決していない男女問題を抱えているのだなあという気がした。
「クローサー」はジュリア・ロバーツ、ナタリー・ポートマンというふたりの女性とジュード・ロウ、クライヴ・オーウェンというふたりの男性が交錯するややこしい関係が描かれ、愛とセックスというテーマが深く考察されている。よくできた映画だと思うけれど、きわどいセリフが多くて、僕はちょっと…という感じだった。
マイク・ニコルズは「卒業」以来、セックスをテーマにしている監督だ。「愛の狩人」も大学の同級生ふたりの数十年にわたる愛と性の遍歴の物語で、女優陣はキャンディス・バーゲンとアン・マーグレットだった。しかし、当時の映画評に「不能になったニコルソンをフェラチオするマーグレット…」と出ていて、僕は見る気を失なった。
しかし、僕とは逆に、カサノバのように生きることを目的にしていたある友人は、「愛の狩人」を見てきて深く感銘を受けていた。彼は高校のときからセックスに深い関心を寄せていたし、当時の高校生としては珍しく様々な実践もしていたようだった。
彼が「愛の狩人」のセックスにとらわれたジャック・ニコルソンについて、滔々と語るのを聞きながら「人の価値観は様々だなあ」と僕は思った。当時の僕は、どちらかと言えば好きな女性と寝ないことをもって尊しとする方だったから、彼のように露骨にセックスについて話すことは嫌悪感を伴った。
「クローサー」でもクライブ・オーウェンは娼婦を買ったことを妻のジュリア・ロバーツに露悪的に告白し、ジュリア・ロバーツはジュード・ロウとどのような体位でセックスしたか、どう感じたかを詳細に話す。互いに傷つけあうのが目的だとしても、聞くに堪えないシーンだった。君たちも一度は愛し合って結婚したのじゃないか、と言いたくなった。
それでもアカデミー賞には四人とも候補になったと思う。ナタリー・ポートマンはクラブで踊るストリッパー役で扇情的なシーンやセックスシーンが多く、いわゆる「体当たり演技」を評価されたのだろう、助演女優賞にノミネートされた。「スターウォーズ」ファン、あるいはアナキン・スカイウォーカーは嘆いたかもしれない。
ナタリー・ポートマンを除く登場人物はそれぞれインテリやアーティストで、ジュリア・ロバーツは写真家、クライブ・オーウェンは医者、ジュード・ロウは作家を目指す新聞記者だった。僕には、ジュード・ロウが演じた新聞記者が面白かった。
登場したばかりのところでジュード・ロウが「死亡欄の担当者」として自己紹介するのが印象に残る。担当としても下っ端でデスクの指示で記事を書く。しかも、いろんな人の死亡を予測して、あらかじめ書いておくのだという。死んでからでは、その人のことを調べている時間が足りないのだろう。
結局、「クローサー」で最も僕の印象に残ったのは、死亡欄担当記者という設定だった。それは僕が欠かさず死亡欄を読み続けているからかもしれない。
●死亡欄の愛読者(?)は多い
 今年の三月、脚本家の佐々木守さんの死亡記事を読んで書いたコラムが出た翌週、佐々木守さんのお嬢さんから長文のメールをいただいた。それによると、お父様が亡くなって各新聞社から電話があり「代表作は『アルプスの少女ハイジ』と『ウルトラマン』でいいんでしょうか? 他はないですか?」というようなことを訊かれ、うまく答えられなかったという。
今年の三月、脚本家の佐々木守さんの死亡記事を読んで書いたコラムが出た翌週、佐々木守さんのお嬢さんから長文のメールをいただいた。それによると、お父様が亡くなって各新聞社から電話があり「代表作は『アルプスの少女ハイジ』と『ウルトラマン』でいいんでしょうか? 他はないですか?」というようなことを訊かれ、うまく答えられなかったという。
僕がコラムで「佐々木守さんの死亡記事の見出しが『ハイジの脚本家』はないよな」と書いたから、お嬢さんは「うまく答えられなかった私が悪い」ように書いていらしたのだろう。しかし、予断を持って電話取材する新聞記者にも問題があるのではないだろうか、それに、父親が亡くなって大変なときに新聞社は平気で肉親に取材するのだなあと、僕は思ったものだった。
そうは思ったものの、死亡記事は確かに調べている時間はない。書く方も大変なのだろうと思い直した。誰を載せ、誰を載せないか、どれくらいの扱いにするか、迷っている時間はない。たぶん死亡欄担当デスクがすぐに決め、指示を出すのだろう。遺族を取材する担当者が決められ、ざっと調べて電話をする…、そんな光景が浮かぶ。
 ところで、十一月二十二日の夕刊にロバート・アルトマンの死亡記事が掲載された。四十行の記事だった。死亡記事としては大きな扱いの方だと思う。ロバート・アルトマンは昔から巨匠扱いされていたけれど、キャリアとしてもかなり長いのだと初めて知った。死亡記事を読んで初めて知ることは多い。
ところで、十一月二十二日の夕刊にロバート・アルトマンの死亡記事が掲載された。四十行の記事だった。死亡記事としては大きな扱いの方だと思う。ロバート・アルトマンは昔から巨匠扱いされていたけれど、キャリアとしてもかなり長いのだと初めて知った。死亡記事を読んで初めて知ることは多い。
僕は「M★A★S★H」(1970年)で初めてロバート・アルトマンという名を知ったから、それほどの年齢だとは思っていなかったが、八十一歳だった。第二次大戦で爆撃機のパイロットだったという。世代的には、ハリウッドで巨匠扱いされても不思議ではない。昨年は、アカデミー名誉賞をもらった。
ただ、僕はロバート・アルトマン作品と相性が悪いのかもしれない。「M★A★S★H」は公開時に評判になった映画だが、僕はあまり楽しめなかった。エリオット・グールドやドナルド・サザーランドという怪優たちをメジャーにした功績は認めるけれど…。
![ロング・グッドバイ [MGMライオン・キャンペーン]](http://ec1.images-amazon.com/images/P/B000KGGBUC.01._SCMZZZZZZZ_V34605652_.jpg) 再起のキッカケになったという「ザ・プレイヤー」も感心しなかったし、「ナッシュビル」以来アルトマンの特徴になった大勢の人が出てくる群像ドラマも僕にはテーマが散漫な感じがしてしまうのだ。「ロング・グッドバイ」も雰囲気描写はいいのだが、原作の改竄は納得できなかった。
再起のキッカケになったという「ザ・プレイヤー」も感心しなかったし、「ナッシュビル」以来アルトマンの特徴になった大勢の人が出てくる群像ドラマも僕にはテーマが散漫な感じがしてしまうのだ。「ロング・グッドバイ」も雰囲気描写はいいのだが、原作の改竄は納得できなかった。
僕にとって感慨深かったのは、十日ほど前に載ったジャック・パランスの死亡記事を見たときだった。たった十五行のベタ記事だったが、「ああ、ジャック・パランスが死んだのだ」という想いが立ち上がってきた。シェーンを演じたアラン・ラッドの死から数えて、四十二年後のことである。
●歳をとると違う側面が見えてくる
 ジャック・パランスはゴツゴツした怪異な顔をしている。見るからに悪党面である。十数年前、アカデミー授賞式に久しぶりに登場したジャック・パランスは、司会のビリー・クリスタルのジョークに応じてタキシード姿で片手腕立てをしてみせた。
ジャック・パランスはゴツゴツした怪異な顔をしている。見るからに悪党面である。十数年前、アカデミー授賞式に久しぶりに登場したジャック・パランスは、司会のビリー・クリスタルのジョークに応じてタキシード姿で片手腕立てをしてみせた。
そのとき、ジャック・パランスはビリー・クリスタル主演「シティ・スリッカーズ」で助演男優賞にノミネートされていたのだ。その夜、ジャック・パランスは見事に助演男優賞を獲得する。それは、七十歳を過ぎた伝説の俳優に対するハリウッドの敬意の表明でもあったろう。
「シェーン」(1953年)が日本で公開されたのは、昭和二十八年十月一日だった。「禁じられた遊び」が九月六日、小津安二郎の名作「東京物語」が十一月三日に公開になっている。「シェーン」の黒ずくめのガンマン役だけで伝説となり、語り継がれる俳優がジャック・パランスである。
 もちろん僕は「シェーン」を公開時には見ていない。若いときに一度、そして、最近、もう一度見た。若いときには「単なるありきたりな西部劇」だと思ったが、最近見て「やはり映画史に残るだけある名作だなあ」と感じた。開拓農民と牧場主の対立、流れ者のガンマン、ガンマンに憧れる農民の息子、彼にほのかな愛情を寄せる農民の妻…、古き良き西部劇の香りである。
もちろん僕は「シェーン」を公開時には見ていない。若いときに一度、そして、最近、もう一度見た。若いときには「単なるありきたりな西部劇」だと思ったが、最近見て「やはり映画史に残るだけある名作だなあ」と感じた。開拓農民と牧場主の対立、流れ者のガンマン、ガンマンに憧れる農民の息子、彼にほのかな愛情を寄せる農民の妻…、古き良き西部劇の香りである。
昔は気付かなかったが、ジーン・アーサーが演じる開拓農民の妻の演技が味わい深い。礼儀正しい流れ者シェーンがやってきたときの警戒心、その警戒心を解きシェーンの人柄に次第に惹かれてゆく心の揺れ、シェーンと夫が牧場主と会うために町にいくことになったときの夫ではなく流れ者を心配する後ろめたさ、別れのせつなさと夫を裏切らなかった安心感…、彼女の内面を想像しながら見れば、それは悲しい恋物語なのだ。
歳はとってみるものである。昔、「ヒーロー西部劇」としか見えなかった映画が「大人の恋愛映画」に見えてくる。見えなかったものが見えてくる。開拓農民を演じたバン・ヘフリンも木石漢ではない。妻がシェーンに惹かれているのを知っている。知ったうえで許し、妻に対する信頼は揺るがない。シェーンに対する敬意も払う。「シェーン」が長い年月に耐える普遍性を持ったのは、その三人の関係をきちんと描いているからだ。
それは、半世紀後に「クローサー」で描かれたのと同じ男女関係である。もちろん「シェーン」の頃には、惹かれあう男女が手を握ることもない。告白もない。しかし、男女の精神性においては、ワイオミングの大自然の中でも半世紀後のロンドンと同じドラマが起こっているのだ。
そんなドラマの中に、ジャック・パランスが悪の象徴として登場する。「シェーン」の中でジャック・パランスの登場シーンはひどく少ない。セリフもほとんどない。それだけで伝説になってしまったのは、よほど公開時のインパクトが強かったのだろう。残念ながら僕は先に伝説を知ったので、「シェーン」を見てもそんなに強い印象はなかった。
映画も後半になった頃、牧場主に雇われた凄腕のガンマンの噂が開拓農民たちの村に伝わってくる。ジャック・パランスが、いかに早撃ちかというエピソードが描写される。それ以前にシェーンが開拓農民の子に銃さばきを見せるエピソードがあり、シェーンの早撃ちは勝てるか、という興味が後半のサスペンスになる。
黒い革のベスト、黒いズボン、黒いガンベルトに黒い革手袋、黒いテンガロンハット…、そんな黒ずくめのスタイルを初めて見せたのがジャック・パランスなのかもしれない。キザに革手袋を直すと、目にもとまらぬ早業で腰の拳銃を抜き、正確に相手を倒した。シェーンは勝てそうもなかった。
僕らが子供だった頃は「早撃ち」という言葉に心をときめかしたものだ。「シェーンは0.3秒なんだぞ」とクラスでも話題になったりした。ガンベルトと玩具の拳銃を買ってもらい、早撃ちの練習をした。いくら早く抜いても、射撃の正確さが必要なのだと気付くのはずっと後のことだった。
【そごう・すすむ】sogo@mbf.nifty.com
息子は初めてひとりで運転して成田から無事帰還し、留学中の娘は復活し、カミサンはフリーパスを買ってロンドンをひとりで観光しているらしい。29日に帰国予定だが、息子が成田まで迎えに行くという。今度は、息子が無事に成田までいけること、カミサンが無事に帰国することを祈る日々である。世に心配のタネはつきません。
デジクリ掲載の旧作が毎週金曜日に更新されています
< http://www.118mitakai.com/2iiwa/2sam007.html
>
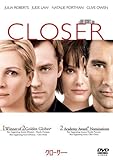


彼が「愛の狩人」のセックスにとらわれたジャック・ニコルソンについて、滔々と語るのを聞きながら「人の価値観は様々だなあ」と僕は思った。当時の僕は、どちらかと言えば好きな女性と寝ないことをもって尊しとする方だったから、彼のように露骨にセックスについて話すことは嫌悪感を伴った。
「クローサー」でもクライブ・オーウェンは娼婦を買ったことを妻のジュリア・ロバーツに露悪的に告白し、ジュリア・ロバーツはジュード・ロウとどのような体位でセックスしたか、どう感じたかを詳細に話す。互いに傷つけあうのが目的だとしても、聞くに堪えないシーンだった。君たちも一度は愛し合って結婚したのじゃないか、と言いたくなった。
それでもアカデミー賞には四人とも候補になったと思う。ナタリー・ポートマンはクラブで踊るストリッパー役で扇情的なシーンやセックスシーンが多く、いわゆる「体当たり演技」を評価されたのだろう、助演女優賞にノミネートされた。「スターウォーズ」ファン、あるいはアナキン・スカイウォーカーは嘆いたかもしれない。
ナタリー・ポートマンを除く登場人物はそれぞれインテリやアーティストで、ジュリア・ロバーツは写真家、クライブ・オーウェンは医者、ジュード・ロウは作家を目指す新聞記者だった。僕には、ジュード・ロウが演じた新聞記者が面白かった。
登場したばかりのところでジュード・ロウが「死亡欄の担当者」として自己紹介するのが印象に残る。担当としても下っ端でデスクの指示で記事を書く。しかも、いろんな人の死亡を予測して、あらかじめ書いておくのだという。死んでからでは、その人のことを調べている時間が足りないのだろう。
結局、「クローサー」で最も僕の印象に残ったのは、死亡欄担当記者という設定だった。それは僕が欠かさず死亡欄を読み続けているからかもしれない。
●死亡欄の愛読者(?)は多い
 今年の三月、脚本家の佐々木守さんの死亡記事を読んで書いたコラムが出た翌週、佐々木守さんのお嬢さんから長文のメールをいただいた。それによると、お父様が亡くなって各新聞社から電話があり「代表作は『アルプスの少女ハイジ』と『ウルトラマン』でいいんでしょうか? 他はないですか?」というようなことを訊かれ、うまく答えられなかったという。
今年の三月、脚本家の佐々木守さんの死亡記事を読んで書いたコラムが出た翌週、佐々木守さんのお嬢さんから長文のメールをいただいた。それによると、お父様が亡くなって各新聞社から電話があり「代表作は『アルプスの少女ハイジ』と『ウルトラマン』でいいんでしょうか? 他はないですか?」というようなことを訊かれ、うまく答えられなかったという。僕がコラムで「佐々木守さんの死亡記事の見出しが『ハイジの脚本家』はないよな」と書いたから、お嬢さんは「うまく答えられなかった私が悪い」ように書いていらしたのだろう。しかし、予断を持って電話取材する新聞記者にも問題があるのではないだろうか、それに、父親が亡くなって大変なときに新聞社は平気で肉親に取材するのだなあと、僕は思ったものだった。
そうは思ったものの、死亡記事は確かに調べている時間はない。書く方も大変なのだろうと思い直した。誰を載せ、誰を載せないか、どれくらいの扱いにするか、迷っている時間はない。たぶん死亡欄担当デスクがすぐに決め、指示を出すのだろう。遺族を取材する担当者が決められ、ざっと調べて電話をする…、そんな光景が浮かぶ。
 ところで、十一月二十二日の夕刊にロバート・アルトマンの死亡記事が掲載された。四十行の記事だった。死亡記事としては大きな扱いの方だと思う。ロバート・アルトマンは昔から巨匠扱いされていたけれど、キャリアとしてもかなり長いのだと初めて知った。死亡記事を読んで初めて知ることは多い。
ところで、十一月二十二日の夕刊にロバート・アルトマンの死亡記事が掲載された。四十行の記事だった。死亡記事としては大きな扱いの方だと思う。ロバート・アルトマンは昔から巨匠扱いされていたけれど、キャリアとしてもかなり長いのだと初めて知った。死亡記事を読んで初めて知ることは多い。僕は「M★A★S★H」(1970年)で初めてロバート・アルトマンという名を知ったから、それほどの年齢だとは思っていなかったが、八十一歳だった。第二次大戦で爆撃機のパイロットだったという。世代的には、ハリウッドで巨匠扱いされても不思議ではない。昨年は、アカデミー名誉賞をもらった。
ただ、僕はロバート・アルトマン作品と相性が悪いのかもしれない。「M★A★S★H」は公開時に評判になった映画だが、僕はあまり楽しめなかった。エリオット・グールドやドナルド・サザーランドという怪優たちをメジャーにした功績は認めるけれど…。
![ロング・グッドバイ [MGMライオン・キャンペーン]](http://ec1.images-amazon.com/images/P/B000KGGBUC.01._SCMZZZZZZZ_V34605652_.jpg) 再起のキッカケになったという「ザ・プレイヤー」も感心しなかったし、「ナッシュビル」以来アルトマンの特徴になった大勢の人が出てくる群像ドラマも僕にはテーマが散漫な感じがしてしまうのだ。「ロング・グッドバイ」も雰囲気描写はいいのだが、原作の改竄は納得できなかった。
再起のキッカケになったという「ザ・プレイヤー」も感心しなかったし、「ナッシュビル」以来アルトマンの特徴になった大勢の人が出てくる群像ドラマも僕にはテーマが散漫な感じがしてしまうのだ。「ロング・グッドバイ」も雰囲気描写はいいのだが、原作の改竄は納得できなかった。僕にとって感慨深かったのは、十日ほど前に載ったジャック・パランスの死亡記事を見たときだった。たった十五行のベタ記事だったが、「ああ、ジャック・パランスが死んだのだ」という想いが立ち上がってきた。シェーンを演じたアラン・ラッドの死から数えて、四十二年後のことである。
●歳をとると違う側面が見えてくる
 ジャック・パランスはゴツゴツした怪異な顔をしている。見るからに悪党面である。十数年前、アカデミー授賞式に久しぶりに登場したジャック・パランスは、司会のビリー・クリスタルのジョークに応じてタキシード姿で片手腕立てをしてみせた。
ジャック・パランスはゴツゴツした怪異な顔をしている。見るからに悪党面である。十数年前、アカデミー授賞式に久しぶりに登場したジャック・パランスは、司会のビリー・クリスタルのジョークに応じてタキシード姿で片手腕立てをしてみせた。そのとき、ジャック・パランスはビリー・クリスタル主演「シティ・スリッカーズ」で助演男優賞にノミネートされていたのだ。その夜、ジャック・パランスは見事に助演男優賞を獲得する。それは、七十歳を過ぎた伝説の俳優に対するハリウッドの敬意の表明でもあったろう。
「シェーン」(1953年)が日本で公開されたのは、昭和二十八年十月一日だった。「禁じられた遊び」が九月六日、小津安二郎の名作「東京物語」が十一月三日に公開になっている。「シェーン」の黒ずくめのガンマン役だけで伝説となり、語り継がれる俳優がジャック・パランスである。
 もちろん僕は「シェーン」を公開時には見ていない。若いときに一度、そして、最近、もう一度見た。若いときには「単なるありきたりな西部劇」だと思ったが、最近見て「やはり映画史に残るだけある名作だなあ」と感じた。開拓農民と牧場主の対立、流れ者のガンマン、ガンマンに憧れる農民の息子、彼にほのかな愛情を寄せる農民の妻…、古き良き西部劇の香りである。
もちろん僕は「シェーン」を公開時には見ていない。若いときに一度、そして、最近、もう一度見た。若いときには「単なるありきたりな西部劇」だと思ったが、最近見て「やはり映画史に残るだけある名作だなあ」と感じた。開拓農民と牧場主の対立、流れ者のガンマン、ガンマンに憧れる農民の息子、彼にほのかな愛情を寄せる農民の妻…、古き良き西部劇の香りである。昔は気付かなかったが、ジーン・アーサーが演じる開拓農民の妻の演技が味わい深い。礼儀正しい流れ者シェーンがやってきたときの警戒心、その警戒心を解きシェーンの人柄に次第に惹かれてゆく心の揺れ、シェーンと夫が牧場主と会うために町にいくことになったときの夫ではなく流れ者を心配する後ろめたさ、別れのせつなさと夫を裏切らなかった安心感…、彼女の内面を想像しながら見れば、それは悲しい恋物語なのだ。
歳はとってみるものである。昔、「ヒーロー西部劇」としか見えなかった映画が「大人の恋愛映画」に見えてくる。見えなかったものが見えてくる。開拓農民を演じたバン・ヘフリンも木石漢ではない。妻がシェーンに惹かれているのを知っている。知ったうえで許し、妻に対する信頼は揺るがない。シェーンに対する敬意も払う。「シェーン」が長い年月に耐える普遍性を持ったのは、その三人の関係をきちんと描いているからだ。
それは、半世紀後に「クローサー」で描かれたのと同じ男女関係である。もちろん「シェーン」の頃には、惹かれあう男女が手を握ることもない。告白もない。しかし、男女の精神性においては、ワイオミングの大自然の中でも半世紀後のロンドンと同じドラマが起こっているのだ。
そんなドラマの中に、ジャック・パランスが悪の象徴として登場する。「シェーン」の中でジャック・パランスの登場シーンはひどく少ない。セリフもほとんどない。それだけで伝説になってしまったのは、よほど公開時のインパクトが強かったのだろう。残念ながら僕は先に伝説を知ったので、「シェーン」を見てもそんなに強い印象はなかった。
映画も後半になった頃、牧場主に雇われた凄腕のガンマンの噂が開拓農民たちの村に伝わってくる。ジャック・パランスが、いかに早撃ちかというエピソードが描写される。それ以前にシェーンが開拓農民の子に銃さばきを見せるエピソードがあり、シェーンの早撃ちは勝てるか、という興味が後半のサスペンスになる。
黒い革のベスト、黒いズボン、黒いガンベルトに黒い革手袋、黒いテンガロンハット…、そんな黒ずくめのスタイルを初めて見せたのがジャック・パランスなのかもしれない。キザに革手袋を直すと、目にもとまらぬ早業で腰の拳銃を抜き、正確に相手を倒した。シェーンは勝てそうもなかった。
僕らが子供だった頃は「早撃ち」という言葉に心をときめかしたものだ。「シェーンは0.3秒なんだぞ」とクラスでも話題になったりした。ガンベルトと玩具の拳銃を買ってもらい、早撃ちの練習をした。いくら早く抜いても、射撃の正確さが必要なのだと気付くのはずっと後のことだった。
【そごう・すすむ】sogo@mbf.nifty.com
息子は初めてひとりで運転して成田から無事帰還し、留学中の娘は復活し、カミサンはフリーパスを買ってロンドンをひとりで観光しているらしい。29日に帰国予定だが、息子が成田まで迎えに行くという。今度は、息子が無事に成田までいけること、カミサンが無事に帰国することを祈る日々である。世に心配のタネはつきません。
デジクリ掲載の旧作が毎週金曜日に更新されています
< http://www.118mitakai.com/2iiwa/2sam007.html
>
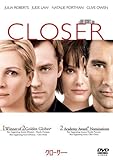
- closer / クローサー
- マイク・ニコルズ ジュリア・ロバーツ ジュード・ロウ
- ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 2006-02-22
- おすすめ平均

 最後まで見てやっと納得
最後まで見てやっと納得 natural and deep
natural and deep 愛とは
愛とは 粋な作品
粋な作品 キャストがもったいない映画ではないかと・・。
キャストがもったいない映画ではないかと・・。

- 愛の狩人
- ジャック・ニコルソン
- ビデオメーカー 1993-10-01

- マッシュ
- ロバート・アルトマン ドナルド・サザーランド エリオット・グールド
- 20世紀フォックス・ホーム・エンターテイメント・ジャパン 2006-02-10
- おすすめ平均

 ハチャメチャな反戦映画
ハチャメチャな反戦映画 天才外科医
天才外科医




























