 ●椎名誠さんの映画作りの本
●椎名誠さんの映画作りの本先日、椎名誠さんの「まわれ映写機」という文庫が目に付いたので購入し、すぐに読み終わってしまった。昨年末に文庫になったもので、単行本は2003年の発売である。僕は、二十年近く前に椎名さんの「風にころがる映画もあった」という本を読んでいるが、椎名さんは自分の映画作りをネタにいくつか本を書いている。
写大(現在の工芸大)出身の椎名さんは月刊アサヒカメラに写真を連載するほどで、僕は「いい写真を撮るなあ」と思っているけれど、本当に熱中したのは映画制作であるらしい。その熱中ぶりは「風にころがる映画もあった」「まわれ映写機」によく描かれている。
僕が初めて椎名さんに会ったのは、水中写真家である中村征夫さんの最初のエッセイ集「海も天才である」の出版記念パーティだった。1985年の初夏だったから、もう二十年以上も前のことになる。当時、僕はカメラ雑誌の編集部にいて、体験取材で水中撮影をやったときの師匠が征夫さんだった。
 僕が初めて中村征夫さんと会った頃、「今度、椎名誠さんと仕事をするんだよ」と言っていたけれど、その後、どんどん二人は親しくなり、征夫さんにエッセイ集を書かせたのも、「海も天才である」というタイトルをつけたのも椎名さんだった。だから、中村さんの出版記念パーティに椎名さんがきているのは当然だったのだ。
僕が初めて中村征夫さんと会った頃、「今度、椎名誠さんと仕事をするんだよ」と言っていたけれど、その後、どんどん二人は親しくなり、征夫さんにエッセイ集を書かせたのも、「海も天才である」というタイトルをつけたのも椎名さんだった。だから、中村さんの出版記念パーティに椎名さんがきているのは当然だったのだ。椎名さんが長編「哀愁の町に霧が降るのだ」を出したのもその頃だったろうか。自伝的エッセイで、それまでのドタバタ的大げさな描写が抑えられ、タイトルのように哀愁が漂う大長編だった。椎名さん言うところの「面白カナシズム」である。面白うて、やがて哀しき…という本だった。そんな人気急上昇中の作家だから僕は気後れし、気軽に声はかけられなかったのである。
僕が最初に買った「本の雑誌」は表紙に「'78年秋/特大号」と入っている10号だった。その中の「文藝春秋10月号464頁単独完全読破」という記事で初めて椎名さんの文章を読んだのだが、あまりの面白さに驚いた。「おれはこの雑誌の編集長だが、めしを喰っていくためにじつはもうひとつ別の雑誌の編集長もやっている」と、その文章は始まっていた。
 それから間もなく椎名さんの処女エッセイ「さらば国分寺書店のオババ」が書店に並んだ。それもすぐに買って読んだが、その本一冊で椎名さんは評判になり、次々に本を出し始めた。嵐山光三郎、糸井重里と並んで椎名誠さんの文体は「昭和軽薄体」と名付けられた。それでも、しばらくは銀座にある流通業界誌の編集長を続けていたのではなかっただろうか。
それから間もなく椎名さんの処女エッセイ「さらば国分寺書店のオババ」が書店に並んだ。それもすぐに買って読んだが、その本一冊で椎名さんは評判になり、次々に本を出し始めた。嵐山光三郎、糸井重里と並んで椎名誠さんの文体は「昭和軽薄体」と名付けられた。それでも、しばらくは銀座にある流通業界誌の編集長を続けていたのではなかっただろうか。中村征夫さんの出版記念パーティでは、たまたま椎名さんは僕の横に立っていたのだが、文章からイメージしていたのとは違い、背が高く精悍な二枚目だった。ワイルドな髪型もさりげなく似合っていた。アウトドア派であるから、肌は陽に焼けて男らしさを振りまいていた。女性読者が多くつくのも納得できた。
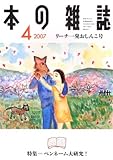 結局、僕が椎名さんと言葉を交わしたのは、そのずっと後のこと、「本の雑誌」の月刊化を祝うパーティが市ヶ谷で開かれたときだった。そのとき、僕は名刺を出してこう言った。
結局、僕が椎名さんと言葉を交わしたのは、そのずっと後のこと、「本の雑誌」の月刊化を祝うパーティが市ヶ谷で開かれたときだった。そのとき、僕は名刺を出してこう言った。──「小型映画」作ってました。
すかさず椎名さんは答えてくれた。
──読んでました。
●椎名誠さんが作った映画を見た
椎名さんが月刊「小型映画」の発売日を待ちかねて買いにいっていた、という話は「本の雑誌」の座談会で読んでいた。「まわれ映写機」にも月刊「小型映画」の話は何度も登場する。8ミリでトーキー映画を作るエピソードでは、別冊「小型映画」を参考にする話も出てきた。
おそらく、それは僕が入社早々に作った「小型映画ビギナーシリーズ」の「8ミリトーキー入門」という特集誌だと思う。入社して三年半たったときに僕は月刊「小型映画」編集部に異動になった。ちょうど椎名さんが映画制作に熱中し、毎月発売日に書店へ走っていた時期に重なるらしい。
映画制作に熱中した椎名さんは、とうとうボレックスの16ミリカメラを購入する。それは「小型映画」の「売ります買います」という欄で見付けた中古品だった。その欄は読者同士の機材の売買を仲介するコーナーで、発売日に本を買う理由はその頁を誰よりも早く見たいからだという読者は多かった。
しかし、その欄は編集部内では人気がなく、新人が担当することが決まっていた。読者からきたハガキを「売ります」と「買います」にわけ、さらにカメラ、映写機、編集機器、三脚などのアクセサリーに分類する。担当者によっては、そのハガキをそのまま印刷会社に入稿する人もいたが、僕はすべて原稿用紙にリライトしていた。
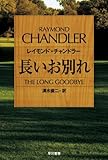 「小型映画」は二十五年前の秋に十月号を出して休刊した。その最終号の編集後記を僕は「映画にさよならをいう方法はいまだに見つかっていない」と結んだ。レイモンド・チャンドラーの「長いお別れ」(清水俊二訳)の最後のフレーズをもじったのである。編集者になって八年経っていた。
「小型映画」は二十五年前の秋に十月号を出して休刊した。その最終号の編集後記を僕は「映画にさよならをいう方法はいまだに見つかっていない」と結んだ。レイモンド・チャンドラーの「長いお別れ」(清水俊二訳)の最後のフレーズをもじったのである。編集者になって八年経っていた。その後、僕はカメラ雑誌の編集部に移り、椎名さんに名刺を渡して「『小型映画』作ってました」と言ったときには、もう休刊してから数年が経っていた。それでも椎名さんは「本当に毎月楽しみにしていました」と言ってくれたのだった。
その椎名さんが本格的に映画を作り始め、とうとうプロのスタッフとキャストで35ミリサイズ(撮影は16ミリ)の劇映画を完成したのは、1991年の秋のことだった。その頃、僕は「ビバ・ビデオ」というビデオ雑誌の編集をしていた。その七号で僕は映画を完成したばかりの椎名誠さんをインタビューしている。
椎名誠監督作品の二作目「うみ・そら・さんごのいいつたえ」は、年末に東京と大阪で特別先行上映会が行われ、1992年初頭から沖縄を皮切りに北海道までの全国上映ツアーが予定されていた。作品上映と椎名さんのトークショーがセットである。
僕は五反田のイマジカの試写室で初号試写を見せてもらい、銀座資生堂地下のザ・ギンザ・アートスペースで椎名誠さんを取材した。そこでは椎名さんの写真展「いとしい人々」を開催しており、インタビュー中も周囲に客が大勢いる状態で、なんとなく落ち着かなかったことを覚えている。
●ハッタリやあざとさとは無縁の正統的で美しい映画
「うみ・そら・さんごのいいつたえ」は中村征夫さんの写真集「白保──うみ・そら・さんごのいいつたえ」にインスパイアされた物語で、沖縄の白保が舞台である。ムービー撮影はすべて中村さんだ。水中撮影の見事さは、さすがに征夫さんだと思った。そのときの取材記事から引用してみたい。
──インタビューの六日前、初号試写を見ることができた。本格派の剛速球のような印象の映画だった。ハッタリやあざとさとは無縁の正統的で美しい映画、見終わって好きになる映画だった。ドラマを無理に盛り上げるようなことはせず、自然と人々が静かに描かれていく。
キャメラワークはフィックスでグングン押してくる。ズーミングを使うのはワンカットだけ。明快なカット割りと編集で正確に見せていく。唯一、ドラマ的なヤマ場は子どもたちの船が流されて行方不明になるエピソードだ。
しかし、無人島の子どもたちのところに海人(うみんちゅ)のコンゾの船が現れ、子どもたちが救われるシーンでは、そのコンゾの船が近づいてくるショットの次はもう救出されて数日たった子どもたちの日常のショットになる。助け出されて喜び合うなどというシーンは描写されない。このスタイルは全編を通して貫かれていて、うまいなあと思うのだ──
そう言った僕に対して、椎名さんは「和田誠さんも、あそこをすごく評価してくれて、あそこで家族が泣きわめいたり、助けられて抱き合って喜んだりするというのがないから、もっともっと深くそのことがわかるなあ、と…」と答えている。
──映画は夜明け前の海辺のシーンから始まり、夏の終わりの明るい海のシーンで終わる。同時にファーストシーンで海人である祖父・国松の手伝いをしていた少年タカシは、ラストシーンで船の舳先に立ち先導するまでに成長している。映画は様々な人々が登場し、様々な物語が語られ、様々な海の表情が描かれる。
特にこのファーストシーンとラストシーンの対照が見終わって印象に残る。真俯瞰で撮影されたファーストシーン、タカシの乗る船と平行にフォロー撮影されたショットから空撮へ続くラストシーン。暗い海と明るい海。ラストシーンに至り再びファーストシーンが新しい意味を持つ──
当時の記事を書き写しながら、今、僕はそのファーストシーンとラストシーンを鮮明に思い出した。椎名さんは真俯瞰のファーストシーンのために浜辺にヤグラ(映画界ではイントレという)を組んだと言った。それは「アラビアのロレンス」の冒頭、オートバイに乗る準備をするロレンスを真俯瞰で撮ったシーンへのオマージュだった。
![S-Fマガジン 2007年 05月号 [雑誌]](http://ec1.images-amazon.com/images/P/B000O75FE0.01._SCMZZZZZZZ_V24562380_.jpg) ──「小型映画」はずいぶん長く読んでいたし、古本屋でバックナンバーを買ったりしたので、けっこう揃えていましたよ。別冊もよく出していましたね。「小型映画ハイテクニックシリーズ」では16ミリについてもやっていたでしょう。ずいぶん役に立ちましたよ、僕には。「小型映画」と「SFマガジン」の発売日が楽しみで、ホントにその日は朝からうれしかったものです。
──「小型映画」はずいぶん長く読んでいたし、古本屋でバックナンバーを買ったりしたので、けっこう揃えていましたよ。別冊もよく出していましたね。「小型映画ハイテクニックシリーズ」では16ミリについてもやっていたでしょう。ずいぶん役に立ちましたよ、僕には。「小型映画」と「SFマガジン」の発売日が楽しみで、ホントにその日は朝からうれしかったものです。「小型映画」についての僕の質問には、そんな風に答えてくれた。そう椎名さんに言ってもらった「小型映画」は休刊から数えると十年が過ぎようとしていた。僕はカメラ雑誌に八年在籍し、「ビバ・ビデオ」に異動して二年目に入っていたのだ。
その「ビバ・ビデオ」も今はない。四年間で二十号まで刊行し、休刊した。今度は編集長として「休刊の挨拶」を僕は書いた。編集者になって十九年めのことだった…
【そごう・すすむ】sogo@mbf.nifty.com
自宅のベランダから見下ろすとしだれ桜が咲いている。この原稿が出る頃にはソメイヨシノも咲いているだろう。毎朝、バス停でバスを待つのが楽しくなる。駅まで桜が続くので、毎年の楽しみだが長くは続かない。
●第1回から305回めまでのコラムをすべてまとめた二巻本
完全版「映画がなければ生きていけない」書店・ネット書店で発売中
出版社< http://www.bookdom.net/suiyosha/suiyo_Newpub.html#prod193
>






















 椎名氏の視点の原点?!
椎名氏の視点の原点?!






